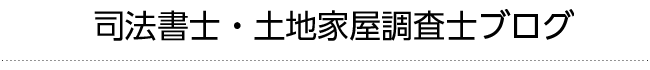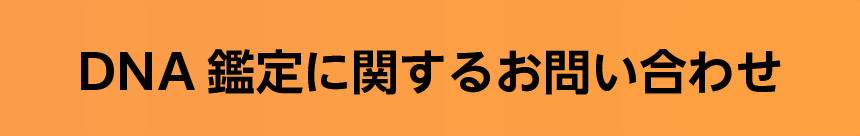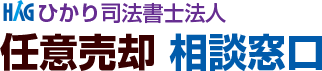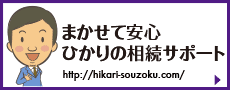【DNA鑑定業務】~DNA鑑定後の問題を一緒に解決~
ひかり司法書士法人では、DNA鑑定の専門機関である株式会社seeDNAと業務提携を結び、法的DNA鑑定の立会業務を行っております。
法的DNA鑑定の結果は、認知や親権問題などで血縁関係を科学的に証明したい方に、裁判や調停等で証拠資料として認められる証明書になります。
弊社が取り扱う法的DNA鑑定は裁判等での証拠として認められるように、第3者である法律家が立会いを行い、DNA採取、サンプルの封印、採取現場写真の記録など、段階ごとに記録を残し、厳格な手順を踏んで作成いたします。
今回は、DNA鑑定後の問題を一緒に解決した事例のご紹介になります。
DNA鑑定の結果によっては、夫婦が離婚という選択肢を選ぶ場面も発生します。
離婚するとなると住むところが変わったり、子供の親権をどうするかなど、たくさんの事を決めていかなければいけません。
今後のことも見据えたうえで様々なことを時間をかけて決めていかなければならないので、名義変更のような事務手続きは専門家へ依頼し、出来る限り手間を少なくした方がよいと思います。
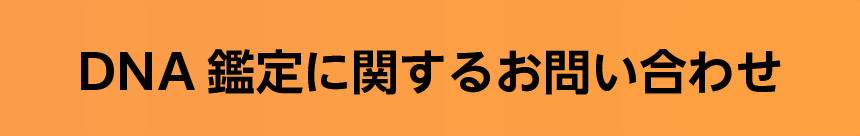
【事例1】ご夫婦共有名義のご自宅を、今後住み続ける奥様名義に変更したい
不動産の名義変更の際にまず確認することは、現在の名義がどなたで、変更後の名義はどなたにしたいのかという点。それとご自宅であれば住宅ローンの有無についての確認が必要です。
住宅ローンの有無によって、その後の手続きは異なります。住宅ローンが無ければ、ご夫婦だけである程度のことが決められますが、住宅ローンがある場合には、そこに金融機関の意向も加わるため、希望通りの名義変更が行えない場合も出てきます。
本件でもご主人様名義の住宅ローンがありましたが、今後は奥様が支払っていく予定とのことでした。住宅ローンは基本的には、住んでいる人と住宅ローンの名義が一致していないといけません。よって、名義変更をする前に、まずは奥様の収入で残った住宅ローンを返済していけるかを金融機関へ審査してもらいます。この審査が通れば、金融機関も名義変更には協力をしてくれることになります。
本件では、無事審査に通り、現在の住宅ローンの名義(債務者)が旦那様となっているところを、奥様が債務を引き受ける形で住宅ローンの名義変更ができることになりました。
【事例2】住宅ローン返済中の自宅を売却したい
マイホームを夫婦共有名義で住宅ローンを組んで購入しましたが、離婚をすることに。
一方の収入だけでは住宅ローンの返済が難しいので、売却をしてそれぞれ別の場所に引っ越しをお考えであった事例です。
本事例の場合、売却して買主へ名義変更をするということになります。よって夫婦間での名義変更ではなく、まずは買主を探すことになります。通常は、仲介業者などの不動産業者へお願いすることになるかと思いますが、本事例で一番大きなポイントは、売却代金で、住宅ローンをすべて返済できなかったという点です。
仮に、住宅ローンをすべて返済できるのであれば、そこまで難しい話ではありません。
しかし、売却しても、住宅ローンの完済金額に大きく足りないような場合、通常は売却することはできません。なぜなら、売却した代金で住宅ローンを完済し、担保が何もない状態で、買主へ名義変更しなければならないところ、住宅ローンを完済できないので担保がついた状態ではだれも買ってくれないからです。
この場合には、通常の不動産取引とは異なり、任意売却という形で売却をすすめていくことになります。
任意売却は、売却代金だけでは住宅ローン完済に足りないものの、その他の条件を付けたりと、担保だけは抹消して売れる状態にする売却の方法をいいます。
もちろん売却代金からの返済で返しきれなかった金額分は、売却後に返済をする必要があります。
任意売却は通常の不動産の売却とは異なる手続きや知識を必要としますので、任意売却を専門に取り扱いされている不動産業者に相談する必要がございます。
ひかり司法書士法人では任意売却を専門に取り扱っている不動産業者と提携しておりますので、専門の不動産業者と一緒に名義変更のご支援をしていくことが可能です。
ご自宅の問題で離婚がしたくてもできない方がいらっしゃいましたら相談だけでも結構です。一度、ひかり司法書士法人までご相談ください。
【DNA鑑定業務】 ~DNA鑑定後の問題を一緒に解決~(2)
2021年9月15日 | 司法書士ブログ / Posted: otts
任意売却の3つのメリット
こんにちは
司法書士の安田です。
今回は任意売却のメリットについてお話したいと思います。
任意売却とは、住宅ローンの返済が滞った際に、裁判所が強制的に売却する競売手続きに対する用語で、裁判所を通さずに売主と買主が売買契約を結ぶ形での売買をいいます。
メリット①
競売に比べて任意売却は、高値で売れることが多い。
競売の場合、裁判所が最低落札価格を決めて、それ以上の金額で一番高い金額で入札した者が取得することになりますが、一般的に最低落札価格が相場よりも安く設定されるので、相場よりも安く売却されることが多くなります。
売買価格から住宅ローンを返済することになりますので、売買価格が高ければ高いほどその後の返済が楽になります。
メリット②
引っ越し費用などを出してもらえることもある。
競売の場合、売買代金はすべて債権者に渡りますが、任意売却の場合には、交渉次第で売買代金から引っ越し費用を出してもらえることがあります。
これは、メリット①にあるように競売よりも任意売却の方が高く売れる可能性があるため、
債権者としても競売ではなく任意売却を認めるメリットがあるためです。
また、競売の場合、場合によっては、強制的に退去をさせれられることがありますが、任意売却の場合は基本的には、買主・債権者との間である程度、引っ越しの時期を相談することができます。
メリット③
ご近所に知られる心配がない
競売の場合、お住まいの不動産が競売物件になったことが、裁判所や新聞などの媒体に掲載されたり、近所の方に聞き込みがあったりと、ご近所に競売になったことが知られてしまいます。これに対して任意売却の場合は、一般の方が知りえない形で売却することもできますし、競売としてではなく普通の売買として売却ができますので、競売になったと近所に知られることはありません。
このように、競売に比べてメリットが大きい任意売却ですが、任意売却で競売よりも高い金額で売却できたとしても、残債務全額を返済することができなければ、残りの債務は売買代金からではなく、ご自身で返済をしなければなりません。
家を手放したから、残りは返さなくてもいいということにはならないのです。
通常、住宅ローンの返済が遅れると、分割ではなく一括で返済しなければいけなくなります。
2,500万円で不動産が売却できたとしても残債務が3,000万円の場合、残り500万円は持ち出し、一括で返済をしなければなりません。
残った500万円を分割で返済していくには債権者と交渉し認めてもらう必要があります。
任意売却は、無理のない形で、家計を正常に戻すための手段となりますので、多くの専門的知識と経験が必要となります。
住宅ローンの支払いが厳しくなっている方は一度弊社にご相談ください。
https://hikari-sihoushosi.com/ninbai/soudan/
2020年12月7日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
任意売却について
新型コロナウィルスによる世界的な景気の低迷。国内の景気にも3月頃から影響が出始めており、給料の減少やアルバイトの雇い止めにより住宅ローンの支払いが難しくなってきた方からの相談が増えてきています。
住宅ローンの支払いができず滞納が続いてしまうと、最終的には不動産が競売にかけられてしまいます。
マイホームが競売にかかると、住むところを失い、さらに残った債務も支払い続けなければなりません。競売での売却価格は一般的には市場価格より低い金額で落札されるため、多くの残債務が残ってしまうことになります。
そこで検討すべきは「任意売却」という方法になります。
任意売却は、競売で強制的に落札される前に、債権者の同意を得て、自主的(任意)に不動産を売却する方法です。
任意売却で不動産を高く売却することができれば、競売で落札されるよりも残債務が少なくなったり、引っ越し費用も捻出できたりと、とてもメリットのある方法といえます。
また不動産の買主と賃貸借契約を締結して、売却後もそのまま住み続けるといった事も可能になります。このような方法はお子様が学校を卒業するまでは校区が変わりたくないといった方に多いです。
それに競売よりも早く売却できるということは、その分の遅延損害金の金額を抑えることができるということになります。通常住宅ローンの遅延損害金は、年利14.6%ととても高額に設定されており、例えば2500万円の残債務がある場合は、損害金だけで年間365万円にもなってしまいます。1日の滞納で1万円。とても恐ろしい金額ですので、住宅ローンを滞納されている方は1日でも早く専門家に相談されることをお勧めします。
メリットの多い任意売却ですが、実績のある専門家に依頼し、可能な限りの好条件で任意売却を成立させることが非常に重要になってきます。
今やインターネットで検索すれば、任意売却の行う専門会社、不動産業者などのホームページが検索結果としてたくさん出てきます。あまり実績のない不動産仲介会社の場合、金融機関との交渉がうまくいかずに失敗に終わるケースもあります。
そのような事にならないためにも、ひかり司法書士法人ではこれまでの任意売却の数多くの実績をもとに、任意売却の制度と手続きの基本を身につけていただくための情報をホームページにて掲載しております。
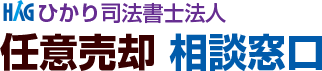
2020年7月29日 | 司法書士ブログ / Posted: otts
新型コロナウィルス対策につきまして
新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため4月7日に緊急事態宣言が発令されました。
当事務所でも感染拡大を防ぐため、手洗い消毒の徹底や会わずに済ませることが出来る要件についてはメールや電話さらにはテレビ電話などで対応することを奨励しております。
このような状況でも、相続登記をしなければならない。財産分与で名義変更をしなければならない。という方や、このような状況だからご自身や親族に何かあった時の対策をしたいという方もいらっしゃいます。
ただ、外出自粛の要請もあり、事務所にお越し頂いたり、こちらから伺っての相談は難しいのが現状です。とはいえ、いつ終息するかもわからない状況でお困りの方も多いと思います。
そこで、当社では、案件にもよりますが、面談不要でお電話・メールと郵送のやり取りで手続きを完了するようお客様のご都合にあわせて業務の進め方を検討・実行しております。
ご相談内容を電話又はメールでお問い合わせ頂き、面談必須ではないご依頼であれば、そのまま、面談不要で業務着手することも可能です。
また、しっかり相談したいという方については、テレビ電話でのご面談も対応しております。パソコンをお持ちでなくてもスマートフォンを使ったテレビ電話でもご対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2020年4月10日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
新型コロナウイルスの影響により内定取り消し、退職を余儀なくされた皆さまへ
約90年の歴史を持つ京都市に本社を構えるひかり司法書士法人では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で企業から内定を取り消された学生や退職を余儀なくされた方を対象に採用活動を始めています。
入社後は京都本社に配属され、不動産登記、会社・法人登記、成年後見業務、相続手続きや測量業務などを中心として、その手続きの補助をしてもらいます。
もちろん、司法書士や土地家屋調査士などの資格取得を目指す場合には、入社後から資格取得のために全面的にバックアップする体制をとっています。
一定期間の研修を終えたのちには、京都に限らず、希望者は東京、大阪、福岡、札幌、滋賀などで勤務することも想定しています。
現代表者が資格を取得した平成13年は、日経平均が8千円台の時代で、自分も就職することに苦労したこともあり、少しでも若い方へ貢献ができればと考えています。
https://hikari-sihoushosi.com/recruit/sihoushosi/
2020年4月6日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人